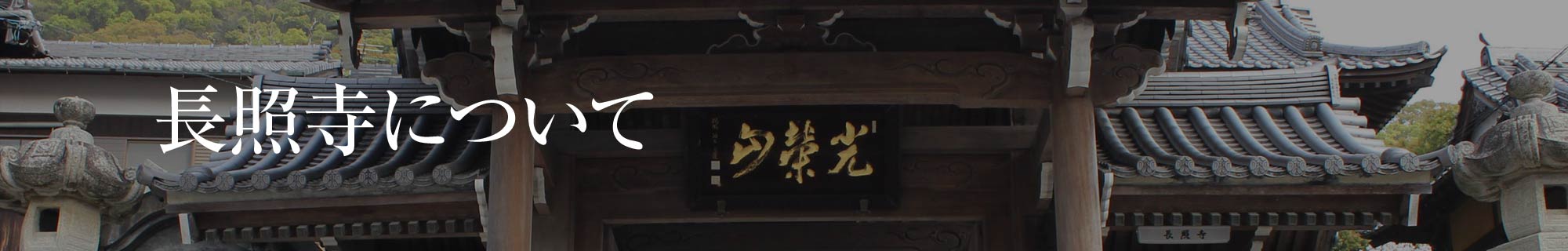沿革
縁起
光栄山長照寺は、寛永八年(西暦1631)本通院日与上人により開創された。
上人は、熊本本妙寺開山日真上人のお弟子で、長崎布教のため派遣された方である。
当時の長崎は、日本唯一の開港地で、キリシタン信仰が盛んな地だったが、
家光による禁教令の実施が厳しくなり仏教寺院の建立が相次いだ。
風頭山々麓には各宗各派が一寺ずつ建ち、寺町が形成されたが、
長照寺開創七年後の寛永十五年に「島原の乱」が起きているので、
その頃の長崎でお題目を広めるのは大変なことだった。
以来、当山は日蓮宗の道場として連綿と法灯を守りつづけ、今日に至っている。
本堂を中心に鎮守堂・稲荷堂・浄行堂・位牌堂・鐘楼が建ち並び、本堂背後より風頭山上にかけては墓地がひろがる。
♦本堂
 寛永十年に建てられてより、宝暦、天明、文政の再建を経て、現在のお堂は、明治七年に建立された。
寛永十年に建てられてより、宝暦、天明、文政の再建を経て、現在のお堂は、明治七年に建立された。
須弥壇には、享保年間造の銘が残る。本堂正面入口には「開会道場」の大きな扁額がかかげられている。
♦鎮守堂
 もと、本堂背後の高所にあったが、参拝に不便なため寛政五年(西暦1793)現在地に移転、再建された。祭神は、妙見神、三十番神、七面天女、清正公、織部氏(長崎開拓者)だが、清正公堂と呼ばれている。
もと、本堂背後の高所にあったが、参拝に不便なため寛政五年(西暦1793)現在地に移転、再建された。祭神は、妙見神、三十番神、七面天女、清正公、織部氏(長崎開拓者)だが、清正公堂と呼ばれている。
♦山門
 寛永年間の古材を一部に残す門だったが、近年傷みがひどくなり、平成十年に、宮崎県産の欅の巨木でもって建て替えられた。
寛永年間の古材を一部に残す門だったが、近年傷みがひどくなり、平成十年に、宮崎県産の欅の巨木でもって建て替えられた。
♦如見の墓
 西川如見(西暦1648~1724)は、当時を代表する天文学者で、著書には日本最初の世界地理の書物といわれる「増補華夷通商考」や、「日本水土考」、「四十二国人物図」、「長崎夜話草」などがある。
西川如見(西暦1648~1724)は、当時を代表する天文学者で、著書には日本最初の世界地理の書物といわれる「増補華夷通商考」や、「日本水土考」、「四十二国人物図」、「長崎夜話草」などがある。
♦長照寺夫婦川別院
 大正5年創立
大正5年創立
住所 長崎市夫婦川町3−5
長崎甚左衛門の弟である織部亮為英を祀っています。
毎年4月11日にお祭りをしています。
♦長照寺矢上別院
 明治40年創立
明治40年創立
毎月15日と30日の午後1時半から法要をしています。
住所 長崎市田中町998
番所橋バス停より徒歩5分